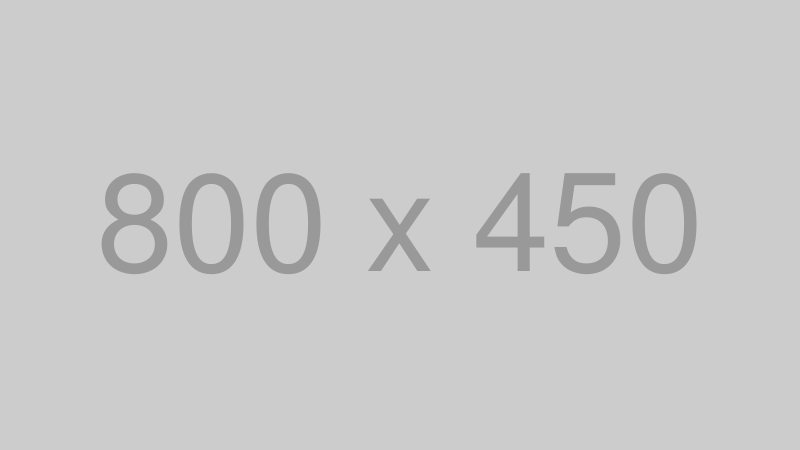国の資源有効利用促進法
岡部理事からの情報です。
国の資源有効利用促進法
資源有効利用促進法は、循環型社会を形成していくために必要な3R(リデュース・リユース・リサイクル)の取り組みを総合的に推進するための法律です。
特に事業者に対して3Rの取り組みが必要となる業種や製品を政令で指定し、自主的に取り組むべき具体的な内容を省令で定めることとしています。
10業種・69品目を指定して、製品の製造段階における3R対策、設計段階における3Rの配慮、分別回収のための識別表示、事業者による自主回収・リサイクルシステムの構築などが規定されています。
| 正式
名称 |
資源の有効な利用の促進に関する法律 | |
| 施 行 | 平成13年4月(平成12年6月公布、平成3年に制定された「再生資源の利用の促進に関する法律」を一部改正) | |
| 目 的 | 我が国が持続的に発展していくためには、環境制約・資源制約が大きな課題となっており、大量生産、大量消費、大量廃棄型の経済システムから、循環型経済システムに移行しなければなりません。この法律は(1)事業者による製品の回収・再利用の実施などリサイクル対策を強化するとともに(2)製品の省資源化・長寿命化等による廃棄物の発生抑制(リデュース)(3)回収した製品からの部品などの再使用(リユース)のための対策を新たに行うことにより、循環型経済システムの構築を目指しています。 |
3Rとは、循環型社会を形成するために必要な取り組みであるリデュース(Reduce)、リユース(Reuse)、リサイクル(Recycle)の頭文字がそれぞれRであることから名付けられた名称です。
(リデュース) 廃棄物の発生抑制
省資源化や長寿命化といった取り組みを通じて製品の製造、流通、使用などに係る資源利用効率を高め、廃棄物とならざるを得ない形での資源の利用を極力少なくする。
(リユース) 再使用
一旦使用された製品を回収し、必要に応じ適切な処置を施しつつ製品として再使用をする。または、再使用可能な部品を利用する。
(リサイクル) 再資源化
一旦使用された製品や製品の製造に伴い発生した副産物を回収し、原材料としての利用または焼却熱のエネルギーとして利用する。
(関係者の責務)
○消費者
製品の長期間使用、再生資源および再生部品の利用の促進に努めるとともに、分別回収や販売店を通じた引き取りなど、国、地方公共団体、事業者が実施する措置に協力する。
○事業者
使用済物品および副産物の発生抑制のための原材料の使用の合理化、再生資源および再生部品を利用、使用済物品や副産物の再生資源・再生部品としての利用の促進に努める。
○地方公共団体
区域の経済的社会的諸条件に応じて資源の有効な利用を促進するよう努める。
○国
教育活動や広報活動を通じて資源の有効な利用の促進に関する国民の理解を深めるとともに、その実施に関する国民の協力を求めるよう努める。
|
資源有効利用促進法について詳しく見る
(消費者)
https://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/admin_info/law/02/consumer/index.html
(事業者)
https://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/admin_info/law/02/entrepreneur/index.html
(地方自治体)
https://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/admin_info/law/02/municipal/index.html